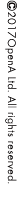「やおや」という表現
2010.5.31 | TEXT
この人なつっこい屋台は、僕の通う東北芸術工科大学前の道路に毎週出現する。大学生と卒業生によるパフォーマンスであり、商売ーすなわち、「やおや」であり八百屋である。最初は時限的な企画として行われた。しかし駆け出しのアーティストが八百屋をやることで、さま、ざまなことが顕在化した。
彼らは郊外の農家に「見てくれが悪くてもいいから、おいしい野菜を分けて欲しい」と声をかけてまわった。「面白いやつらがいる」というワワサはウワサを呼び、いつのまにかちょっとした農家ネットワークができあがる。今では米からアイスプラントという塩を吸収して育つ不思議な野菜まで、さまざまなラインナップが揃っている。
彼らは「やおや」を表現としてやっている。そういう意味では商売ではない。しかし、商売をしようとすることで、今まで顕在化しなかった農業の流通に一石を投じる。現実を揺さぶることはアートにとって重要な役割。何より、その存在感がチャーミングだ。
何をもって表現か、何を持って商売か。何をもって「やおや」で、何をもつて八百屋か。その際をあえて暖昧にしているのがこの作品の問題提起だろう。
今、現代アートの一部は、商業のラインに完全に乗っている。アートマーケットは、株価より世相に敏感な経済市場でもあり、時に投資の対象でもある。それがダイナミズムもあるが、それだけを見ていると、「アートって何?」という壁にも当たる。かといって、閉じた世界だけでしか通用しない独りよがりの表現を、僕は嫌いだ。
「やおや」は、その聞を素直に、ささやかに揺れ動いていて、なんだかとても危うい。それが彼らにとってのリアリティなのではないだろうか。表現の質を保ちながら、いわゆるアートマーケットとは違うマーケットを築けるか。それが問題だ(笑)。
*こちらの記事は季刊誌『オルタナ18号(2010年4月発売)」に「「やおや」という表現」というタイトルで掲載された記事です。
(文=馬場正尊)