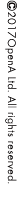僕のインタビュー論、 言葉を探しに。
2014.2.23 | TEXT
僕はかつて雑誌の編集長をしていて、その頃はたくさんの人にインタビューを行った。今ではインタビューを受ける方が多いのだけど、人の話を腰を据えて聞く、という仕事は大好きだ。日本語では「傾聴」ということになるだろうか。その人が何者で、どのようなプロセスでここに立っているのかを探って行く作業がいい。
今、新しい本の取材を始めてる。この時代の、パブリック空間のつくり方を探求する本。インタビューを中心に構成しようとしている。それで、僕が気になって仕方がない人々に対しロングインタビューを始めた。久々の感覚だ。その感覚を思い出しながら、僕なりのインタビュー、人の話を聞く技術について書いてみたい。これ日常的にもけっこう使える。例えば女の子にも・・・?
僕のインタビューはいたってシンプルだ。
・ まずその人の仕事をしっかり調べる(当然です)。
・ 聞きたいことを箇条書きにする(具象から抽象へと質問を並べる。最初は具体的なことが話しやすく、空気がなごんできたら抽象的な話題へと展開)。
・ 成功について聞く。
・ 失敗について聞く(そこに本質が隠れていることも多い)。
・ その人もしくは話題の本質を射抜くひとつの言葉を探しながらインタビューを進める。
僕のインタビューは基本的にこれを繰り返している。
もちろん、与えられた時間によって方法はずいぶん違っている。10分しかない場合はいきなり本質に切りこまなければならないし、あらかじめ答えを想定したような質問になってしまうこともあるだろう。1時間以上ある場合は、多少は本質のまわりをウロウロしてもいい。そうしているうちに、相手の言いたい本来のことが像を結んでいくこともある。
インタビューとは、その人の思考の海の底にたまっている言葉を、質問を投げかけることによって攪拌する作業であると思う。かき混ぜ過ぎてもいけない、シンプルな質問で相手に数多く話させる、それがいいインタビューだ。そして、巻き上げられた言葉の中から重要なフレーズを丁寧にすくい上げる、そんな感じだ。
人間は考えていたとしても、それが言葉や文章といった具体的なフォルムにまでは至ってはいない場合が多い。イメージの塊のようなもので、インタビューは時として、その雲のようなイメージを言葉へと固める作用を起こすこともある。例えば、ある単語がポッと出た瞬間から、その人が抱えていたイメージが具体的な言葉に置き換えられて、スラスラと口から溢れ出す。インタビューという行為が言葉への定着をアフォードしている。そういうインタビューができると、とてもうれしい。インタビューとは、僕にとって言葉を探すための手段である。
あまりメモはとらない。その代わり、できる限り相手にコミットしようとする。まずその人がどんな人間なのかを知りたいと素直に思う。その思考の体系をつかみたいと思う。メモは会話のなかの輝く言葉だけをピックアップし、それだけを書くにとどめている。それで十分話の前後は記憶され、つながっていくものだ。
コミットメント、それがインタビューにとってはとても重要な要素だと思っている。僕の好きな二人の作家が、共にインタビューをベースに作品をつくっている。トルーマン・カポーティと村上春樹。その両方がコミットメントという単語を使って自らのインタビューを説明していた。カポーティの膨大なインタビューの集積から生み出されたノンフォクション小説『冷血』。そのインタビューの際、メモはまったく取っていないと言われる。そのかわりインタビュー相手へのコミットメントに全力を注いだ。
村上春樹のインタビュー集『アンダーグラウンド』の「はじめに」に、その本におけるインタビューの方法が率直に書かれている。その真摯な姿勢に感動し、そして実践的な意味でも学ぶことはとても大きかった。それを読むことを薦めたいが、そのなかで相手へコミットメントと距離感の置き方についての記述は、分野が違っていて、仕事やプロジェクトのためのものだとしても十分に参考になると思う。
二つの作品から、聞き手によって、同じ人からもたらされる情報量も、密度も、そして言葉の質もまったく違うものになるのだということを学んだ。だからインタビューという作業は、質問する側の資質も問われているものだと思う。それでもインタビューは、その人の人生の一部を追体験するようで、好きな作業のひとつだ。