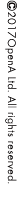2020年の東京郊外
2014.4.30 | TEXT
東京郊外、多摩に嫁の実家がある。サラリーマン時代の約15年前に住んでいた。この正月、年始のあいさつのついでに、その街をひさびさに散策した。
京王線の聖蹟桜ヶ丘。新宿から特急で30分、典型的な郊外だ。この街は1990年代後半に宮崎駿の『耳をすませば』の舞台となったり、田村正和主演のトレンディドラマ『男たちによろしく』の舞台になったりと、輝ける郊外のモデルだった街。僕が住んでいたのはまさにその頃、街は華やいだ雰囲気だった。京王電鉄のデータを調べると乗降客数のピークもその頃に記録されている。現在は緩やかな減少傾向にある。
家族で久々に訪れたその郊外、思い出にしばし浸ろうかと周辺を歩き回ってみると、想像していた感傷とは違う種類の感傷に襲われることになった。
まず賑やかだった駅前に空き物件が目立つ。行きつけだったカフェやレストランはなく、クリーニング屋やラーメン屋など日常に根ざした機能だけが残っている。静かにゆっくりと、街が変化している。タクシー乗り場を見ると、そこにはおみやげを抱えた帰省の家族連れが多く並んでいる。かつては東京から地方へと帰省したが、今では都心から郊外へ帰省する。馬場家もそのうちの一組なのだが、まるで郊外が地方都市のようなポジションに推移している。想像以上のスピードで郊外の人口減が進んでいるのを風景から感じ取れる。切実な郊外の未来を予感させる年始の風景だった。
2020年のオリンピックに向けて都心部の開発のスピードは増すだろう。人口は増え、都心居住の傾向は強まる。そのなかで郊外の人口はさらに中心へと吸い取られ空洞化は進んでしまう。高齢化も避けられない。
そのとき郊外はどうするだろう。かつてほどの人口や活気は取り戻せないにしろ、幸せな生活をバランスよく維持する方法はないのか。
かつて住んでいた聖蹟桜ヶ丘の風景の変化が、改めてそれを考えさせた。
それを解く鍵が「新しい居住」にあるのではないかと考えてみた。
今まで郊外はひたすら「住む」とう単機能を追求して成長してきた。それを補完するのは郊外の大型店舗。まとめて居住専用の家の不足を補完する機能。結果生まれたのが「住む」ことに純化した今の風景だ。
それを再編し、多機能が混ざり合った郊外をイメージしてみたい。単機能だった家をほどき、開き、複数の機能を持った家へと読みかえる。
そもそも近代以前は、家で家畜飼ったり、何かつくって出荷していたり、居住単機能の家なんてなかった。居住と生産と消費が混在していたのだ。
これからの郊外を楽しくするのは、核家族に閉じたビルディングタイプであった家の概念を、他者や、街や、社会に開くことから始まるんじゃないか。
僕らはいつのまにか住居を「住むための機械」と思い込んでしまっていた。それは近代の呪縛だったかもしれない。
近代がつくった幸せな郊外は今、崩壊しようとしている。だとするならば既存の概念を捨て、新しい居住のビルディングタイプを模索しなければならない。
例えば家の一階がパブリックに開かれ公園化している。そこが個人経営の小さな図書館になっていてもいいし、保育園のようになっていてもいい。
家の機能を開放したとき、それは多様なノイズが入り込む余地をたっぷり持っている。2020年に向け、僕らは都心だけでなく郊外の未来も描かなければならない。
*こちらの記事は季刊誌『ケトル vol.17(2014年2月28日発売)」に「馬場正尊は2020年の東京郊外について想う」というタイトルで掲載された記事に加筆したものです。
(文=馬場正尊)