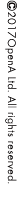2013.8.23 | TEXT
そのホテルは上海の黄浦区の雑踏のなかにある。一見、廃墟のようにしか見えない。外壁はくたびれ、ペンキは今にも剥げそうにめくれ上がっている。そんなビルの一角に、小さなガラスの扉があって、そこから漏れる光から、かろうじてこのビルが稼働していることが感じられる。少し重い、そのガラス扉を聞くと内部は吹き抜けの大空間。かつてここは工場かなにかに使われていた痕跡が色濃く残っている。錆びた鉄骨の柱や梁がそのまま、荒々しく露出している。
スッと伸びたカウンターデスクと、奥にスーツを着た端正な女性コンセルジユという最小の記号が、この空間がかろうじてホテルのエントランスであることを担保していた。
たくさんのリノベーションを手掛けてきたし、ミニマムなデザインで再生する仕事を得意としてきたのだけど、廃墟をこれほど廃墟のままに放り投げた設計はさすがに初めて見た。
薄暗さに少しずつ目が慣れてくると、その放置が計算され尽くしたデザインであることが明らかになってくる。荒いままのベース建築に、慎重に直線的なフォルムや素材がぶつかっている。その微妙なコントラストがいたることろに散りばめられている。奥のパーにはビビットな色の精子がポツポツと置かれ、セピアな空間にピリッと彩りを与えている。
さらに深く入って行くと中庭があり、そこに面した大きなガラスの扉を引き込むと、レストランと中庭はひとつの空間としてつながるようになっている。中庭に面した窓の大きさは大小バラバラで、空間に独符のリズムを与えている。
稼働しているかどうかさえ疑わしい外観の印象は完全に裏切られ、そこには洗練された空間が存在していた。
このホテルの名は「Water House Hotel」、段計はNeri & Hu Design and Research Office で、ハーバード出、中国系の建築家のようだ。最近、中国への出張が多く、いろんなホテルに宿泊するが、このホテルを見ながら中国のデザインもここまで来てしまったか、という感があった。
中国はデザインの実験場になっている。北京オリンピックのメインスタジアム「鳥の巣」や、水泡が寄り集まったようなカタチが話題を呼んだ「ウォーターキューブ」がその代表格だろう。国家規模の大建築だけではなく、民間企業や個人がつくる小さな建築にも洗練と工夫が織り込まれているものをよく見かける。
法規的な制限がまだ甘いことや、いわゆるデザインの常識のようなものが存在していいないことなど、中国は実験的な空間が生まれやすい環境下にある。そのデザインの担い手の多くは、海外に留学していた中国人か、もしくは海外で育って中国に戻って来た人材たち。彼らの感性はヨーロッパ、アメリカ、そして日本のデザイン・ボキャフラリーによって形成されている。彼らは成熟下の国では実現できない実験をしているようにみえる。だから今、中国のデザインは伸び伸びとして、コンセプトを躊躇なく、率直に表現したものが多い。それは観ていてときにすがすがしい。
ウォータハウスの、むき身のデザイン風景を見上げながら変化する中国のデザイン潮流を感じていた。
*こちらの記事は季刊誌『ケトル vol.13(2013年6月21日発売)」に「馬場正尊は上海のホテル「ウォーターハウス」にデザインの実験場、中国の空気を感じる」というタイトルで掲載された記事に加筆したものです。
ケトル
(文=馬場正尊)
2013.8.19 | TEXT

佐賀県伊万里市、僕の生家。
田舎の祖母が他界してしばらく経つ。93歳、大往生である。
亡くなってから最初にやってくるお盆(九州では8/13~15)のことを初盆といい、田舎では霊前を丁寧に飾り、親戚や近くに住む人々が故人をしのびにやってくる。アポイントをとって来るのではなく、みんなフラリとやってくる。だから家族は盆の3日間、ずっと家にいてお客さんを迎えなければならない。
こんな風習があったことは知らなかった。帰省の飛行機が混んでいて、予約もとりにくいこの時期に田舎に帰ることはなかったが、「ときには、盆くらい帰ってこい」という命で久々にこの時期を実家の九州・伊万里で過ごした。
僕にとって、その3日間は不思議な体験だった。
次々と知らない人がやってくる。遠い親戚、商店街の人々、故人の友人(ほぼ80代後半)……。時間はゆっくり流れている。
ふらりとご近所さんがお参りに来る。ひとしきり故人の思い出話や、たわいもない世間話をする。最近、街がどう変わったか、自分の体がどれくらい思い通りにならなくなったか、都会に出た息子たちがどれくらい帰ってこないかなどを話している。
訪ねてくる遠い親戚には顔も知らない人も多く、即席の家系図を書きながらつながりを確認する。田舎なので血縁が複雑に絡み合っていて、なかなか全貌が理解できない。まるで横溝正史の小説のようだな、と思いながら、そこにあったであろう人間ドラマを夢想する。
来客は驚くほど多い。3日間、ほとんどひっきりなしに人が訪ねてくる。僕は田舎の家の長男として、日頃とはまったく違う言葉(方言)と内容の会話をした。
中庭に面した部屋で、かすかに通る風を感じ、うっすらと汗をかきながら、座りっぱなしで静かな時間を、ただ過ごす。ケータイで電車の乗り換え案内サイトを確認しながら、分刻みで移動やミーティングを繰り返す日々とは大違いだ。しかし、伊万里の寂れた商店街の日常の時間の流れは、こんなものなのだろう。
そういう日を3日続けながら、僕の東京での日常は、もしかして極めて特殊な街と時間のなかにあるのではないかと思えてきた。そこには隙間なく思考や行動が滑り込んできて、空白の時間が極めて少ない。意味で満たされた日々。
時々、おつかいを頼まれて外を歩く。
亡くなった祖母によく連れていかれた近くのデパートは、あるにはあるのだけど人影はまばら、華やいでいた頃の面影はない。帰りに、よく遊んだ小高い山の上の公園に10数年ぶりに行ってみると、広かったはずの公園が意外なほど小さくて驚いた。遊具は錆び付いて朽ちかけ、売店は物置になり、展望台は立入禁止になっていた。もはや遊びにくる子どもはいない、ぽっかりとした空間になっていた。確実に時間が過ぎているのを、いやおうなしに実感する。
15日の夜、近くの川で精霊流しが行われた。長崎の精霊流しが華やかで有名だが、隣の佐賀県の各地でもそれは行われている。手づくりの舟に提灯や供え物を乗せて川に流す。近所に住んでいる人々がなんとなく集まってきて、柔らかな光は水面に揺れながらゆっくり流れていく様子を眺める。僕も橋の上から、光の帯が遠のくまで追いかけ続けた。うまく表現できないが、なんだか初期化されたような気分になった。
暑い夏の静かな3日間。
2013.8.17 | TEXT
大阪・道頓堀の空地に設計をしていた「角座」が7月末日にオープンした。 かつて道頓堀は上方の演芸の中心で、そこには、浪花座、中座、角座、朝日座、弁天座と「五座」と呼ばれる芝居小屋が存在していた。しかしいつしか道頓堀は演芸の色が薄まり、角座も壊され空地になっていた。 そこに半仮設的な劇場をつくり、道頓堀の演芸復活のきっかけをつくろう、というのがこのプロジェクト。実現まで紆余曲折あって、かれこれ3年以上かかっている。
新しい角座の最大の特徴は、街にオープンであるということだ。劇場の中はガラス張りで外から丸見え。劇場の活気や気配が街ににじみ出るようなつくりになっている。 芸人たちがリハをしていたり、スタッフが舞台を建て込む様子が垣間みえる。それが今から始まる笑いを予感させる。舞台が跳ねた後は、観客とともに余韻が広場に漏れ出る。ブラックボックスではなく、あえて街に開いた劇場だ。 劇場空間には独特の色気のようなものがあって、それは映像ではなかなか伝わらない。生き生きとした舞台ならではの魅力を、通りを歩く人々に身近に感じてもらいたかった。
前の広場は劇場と街をつなぐオープンエアのホワイエであり、同時に道頓堀の新しい公園でもある。舞台の前後に一杯やってもいい。劇場に用がなくてもフラリと立ち寄ることも自由だ。通りの延長のように、広場も劇場と同じように街に開かれている。
さまざまな飲食の屋台が集まり、大阪の旬の食べ物が出る。そのラインナップも味も、およそ屋台とは思えない。例えば夏の夜風にあたりながら冷えたビールをぐっと飲む、冬にスはトーブにあたりながら熱いスープを味わう。道頓堀のネオンを感じながら、喧噪のなかで過ごす時間をつくりたかった。 もしかすると、芸人が屋台で店員をやっていたり、突然コントを始めて居合わせた客を笑わせたり・・・。この広場ならではの意外な出来事も起こるかもしれない。楽しむ側も、楽しませる側もごっちゃになった、さまざまなハプニングが起こる、そんな笑いの広場になればいい。一年じゅう縁日をやっているような空間だ。
角座再生に合わせて、松竹芸能のオフィスやスクールも劇場の隣に引っ越してきた。道頓堀を会社全体で盛り上げようという覚悟の現れだと思う。スクールに通う生徒も、オフィスで働くスタッフも、常に生の笑いの現場を目の当たりにしながら過ごすことになる。
最初は劇場だけだった計画は、いつの間にかにどんどん大きくなり、建物のなかに入りきれなくなった。外に追い出されたのはなんと社長室で、トラックの改造した、これまた丸見えの部屋になった。劇場も、広場も、社長室もすべてオープン。道頓堀に開いて行く。 この角座と広場から、新しいお笑いが街全体に広がってく、そんなイメージを持ちながらこの場所をデザインした。
現在、角座とその広場は連日、にぎわいを見せているようだ。新しい笑いと、上方の演芸が再び、この場所から育って欲しい。 道頓堀のど真ん中、ぜひ立ち寄って下さい。
2013.8.14 | TEXT
今日、独りで秋葉原をトボトボ歩いていた。
すると、居酒屋の客引きの女の子に声を掛けられた。どの街でもある出来事だが、秋葉原が違うのは、その娘がちょっと幼な可愛いく、オタクの空気をまとっていたこと。
そのときのフレーズが、これだ。
「一緒に、飲み飲みとか、しちゃいませんかー?」
めずらしくクラッときている自分に驚く。なぜだろう?
いつもは自動的に耳をスルーさせて聞き流す客引きのフレーズ。
しかし、もし後に打ち合わせが入っていなかったら、つい飲み飲みとかに行ってしまいそうな衝動に駆られ、それに自分自身が驚いていた。
なぜ、このときの秋葉原フレーズは僕の気持ちを揺さぶったのか?
飛び乗った山手線のなかで、その理由を分析を行った。
そこで秋葉原の言語感覚のすごさを思い知ることになる。
分節に分解してみる。
「一緒に/飲み飲み/とか/しちゃいませんかー?」
一緒に >> あ、一緒なんだ
飲み飲み >> 飲むだけじゃなく、飲み飲みなんだ
とか >> とか? 他にもあんのかな
しちゃいませんか >> しちゃうくらいなら、まあいいかな
四つの文節のすべてに罠が仕掛けてある。
そして、ひとつの分節にも無駄がない。
僕の脳はごく素直に、
「一緒に/飲み飲み/くらいなら/しちゃっていいかなー」
と反応していたのだ。
この研ぎすまされたトラップフレーズの構成。もはや洗練された文学の域だ。
あー、一緒に飲み飲みとかしてー。