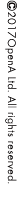東京カプセルホテルワンダーランド
2002.7.30 | TEXT
その日、僕が目黒のカプセルホテルに泊まってしまうことになったのには、いくつかの理由がある。不幸な偶然が重なった、としか言いようがない。「Traveling Life」が、この日記のテーマになってはいるものの、まったく東京の事務所で仕事をしている日にまで、カプセルホテルにお世話になってしまうなんて、オレは何をやってるんだろう。
その日、僕はコンペの提出を前に事務所で徹夜覚悟だった。ただ、どうしてもお風呂に入りたいために、最近入会した事務所近くのスポーツクラブに行くことにした。スポーツクラブであるにもかかわらず、そこは僕に、事務所泊まりのときのお風呂として使われてしまっていて、この日も「ちょっとエグザス銭湯行ってきます」と、夜の11時近くに財布片手にふらりと事務所を出た。それが、この日の不幸の始まりだった。
すっきりして事務所に戻ると、鍵が掛かっている。スタッフがみんな帰ってしまっているのだ。仕方なくポケットに鍵を探すと、ない……。スタッフを呼びつけようと携帯電話を探すと、それもない……。全部、事務所のなかにあるのだ。観念して、自宅に帰ろうと思ったのだが、次の瞬間、その鍵も他と同様、事務所の中にあることに気がつく。一瞬、混乱に陥った。
オレはどうすればいいのか?
数十秒、さまざまな行動のオプションを検索するも、まったく解決策がないことに、次第に気がついていった。
スタッフの携帯や自宅の番号は、誰一人として暗記していない。すべて携帯電話のメモリのなかだ。 スタッフの自宅の所在も、誰一人として知らない。
泊めてくれと頼める女性はおろか友人の一人もいない、というかその連絡手段はまったくない。
それが次々に頭の中で整理されていった後、僕はあることに気がつく。
「オレって、なんて孤独なやつなんだ……」
そして僕は途方に暮れる。
仕方ない。気を取り直して、近くのビジネスホテルに泊まることにする。ビールでも飲みながら、テレビを見て眠りに落ちるのもいいじゃないか。神様が「休め」って言ってるんだな、きっと。
僕は立ち直りは早い。
携帯のない僕は、近くの電話ボックスに、ほんとうに久しぶりに入り、新宿近辺のビジネスホテルに電話し始めた。最初は、ちょっと小洒落たネーミングのホテルを選別していたのだが、どれも満室。余裕がなくなり、かたっぱしから電話するも全部満室。いったいどうなっているんだ。こんな独りの夜にセンチュリーハイアットに泊まるほど、僕は稼いでいなし、そもそもそんなに切ない夜は過ごしたくない。
僕は、さまざまな方法と記憶を必死に検索した。
「目黒に事務所の鍵を持っている友人がいる」
ふと気がついた。部屋番号までは覚えていないが、その事務所には行ったことがあって、場所はわかっている。事務所をシェアしているメンバーのひとりだ。僕は、わらをもすがる思いで、最終の山の手線で目黒に向かった。なぜか手には濡れたタオルを持ったままで。そもそも、今は銭湯(正確に言うとスポーツクラブ)の帰り道でしかないはずだった。
目黒についた。友人の事務所のあるマンションに行った。オートロックだった。部屋番号がわからない。連絡のとりようがない。目の前まできているのに。友人はこのビルの空間の塊のなかの何処かにいるはずなのに。
どうしようもなかった。
そしてまた、僕は途方に暮れる。
トボトボと目黒駅までの道を引き返し始めた。そんな僕に追い打ちを掛けるように、雨が降ってきた。その雨足はあっというまに激しくなる。もう、どうでもよくなってきた。泊まるところも、身を寄せるところもない。電車もなくなってしまった。
仕方なく、目黒駅の交番に入り「あの、この近くに泊まるところないっすかね?」と訪ねてみた。
そこで、カプセルホテルが近くにあることを知る。もうなんでもいい。まずは、そこに行ってみるしかない。
駅から歩くこと5分、それはあった。ふつうのオフィスビルの2階部に、まさしくカプセルを並べただけの空間。
「空いてますか?」
「アイテマス」片言の日本語だった。
助かった。これでなんとか眠る場所が確保できた。一泊3500円。キーは部屋の鍵ではなく、ロッカーの鍵。浴衣に着替え、狭いロビーの自販機でビールを買って黒いボロボロのソファに座って飲み始めた。うまい、安堵感でいっぱいだった。
でも、まだ寝るにはずいぶん早い時間だ。
隣にいた男たちは、中国語で会話している。顔に「不法滞在」と書いてある(ような気がした)。
彼らが去って、今度は真っ黒に焼けた男二人組。最初は、携帯電話の話をしていたのが、そのサイレントモードのバイブレーターの話に移行し、いつのまにかに性器に入れるバイブレーターの話題になっていた。
やっとゆるやかに睡魔がおそってきて「カプセル」のなかに入る。ほんとにカプセルだった。カプセルが並ぶ風景は映画『マトリックス』を思い起こさせた。
インテリアは、超クール。キューブリックのようような70年代デザイン。小さなテレビや、空調、照明のツマミも、カプセルの内部空間のなかにビルドインされている。究極のミニマムな機能空間だ。フューチャーシステムズのデザインのような曲線が美しい。興奮して眠れなくなった。こんな空間をアートでもなんでもなく、日常のなかに当たり前に導入するのは日本くらいなもんだろう。おまけに、ビルの違う階には普通にオフィスが入っている。オフィスとまったく同じビルディングタイプのなかがホテルになっているのだ。
今度、海外から建築家やデザイナーが来たら、間違いなく招待しようと思った。
いつもは考えない、さまざまなことを考えているうちに、やっと少しずつ眠くなっていった。
こうして、僕のワンダーな夜は更けていった。ぐっすり眠ることができた。快適な朝を迎え、シャワーを浴び、何事もなかったように事務所に向かった。いつもより、ちょっと早めの時間に。
クセになりそうだった。時々、泊まりに行こう。
*こちらの記事はWEBマガジン「REAL TOKYO」に「東京カプセルホテルワンダーランド」というタイトルで掲載された記事です。
(文=馬場正尊)